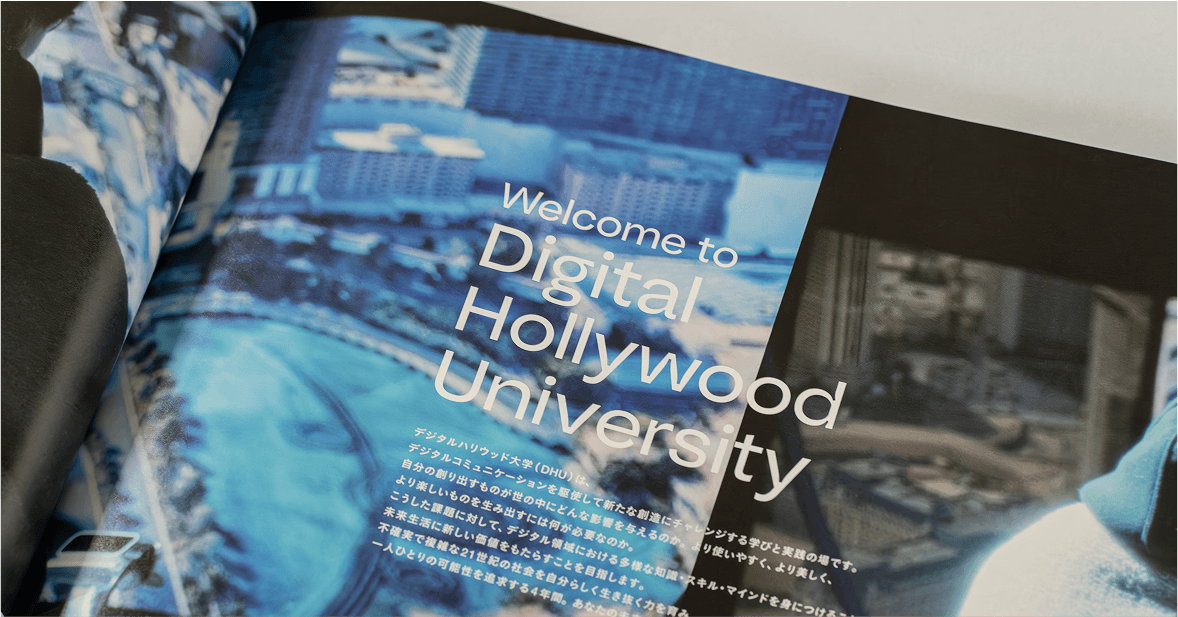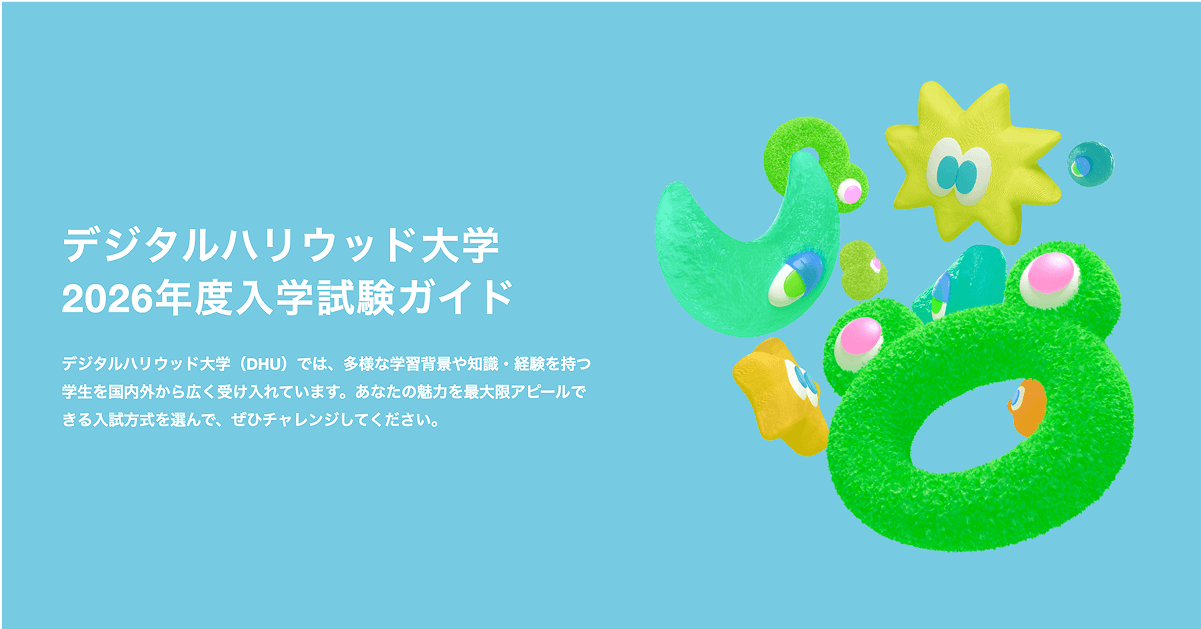ニュース&イベント
【開催レポート】私がAIの社会実装を進める理由~今この瞬間を生きる~

【開催レポート】私がAIの社会実装を進める理由~今この瞬間を生きる~
開催日時
2019年12月13日(金)19:20~21:00
場所
デジタルハリウッド大学・駿河台キャンパス
東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ アカデミア3F
駿河台ホール
レポート
デジタルハリウッド大学 2年 土屋 康祐
2019年12月13日、デジタルハリウッド大学では、特別講座「私がAIの社会実装を進める理由~今この瞬間を生きる~」を開催しました。
講師を務めて下さったのは、本学の特任准教授である起業家、アーティストの三浦亜美氏です。本講座ではまず、AIの社会進出に関する事業について紹介していただいた後に、実際にAIが普及すると社会にどのような影響があるのかなどについて解説していただきました。

自身のバックグラウンドについて
三浦氏は、多くのアスリートを輩出してきた家に生まれ、「筋肉至上主義」と言えるような育ち方をされてきたそうです。そんな中では、自分では全く疑問に思わないようなことでも、学校の友人たちとは大きく異なるような家庭方針もあり、そういった環境の中で自分にとっての「当たり前」は実際のところ当たり前でもなんでもなく、それぞれの人物にそれぞれの当たり前が存在するということを常に考えていたそうです。アスリート一家としての教えから、人間の身体に対してリスペクトを持っていたこともあり、人というものの面白さに気づいたことが、後の三浦氏の活動につながっていきます。
また、今日何をするのか、明日は何をするのか、次の大会までには何を目標にするのかなどといったアスリートらしい考え方から、「今」を感じ、今この一瞬について何をすればいいのかということを真摯に考え、実行に移すことの大切さを重視するようになったと三浦氏はおっしゃっていました。
伝統産業とAI
人と人、日本と世界、地方と東京、過去と未来、伝統文化と最新技術。あらゆるものの「あいま」をとりもち、新しい価値を創り出す。アーティストとして課題を問いかけ、起業家としての課題を解決し、世界にある「よいもの」を継承していく。というコンセプトをベースに、株式会社imaを設立した三浦氏は、テクノロジーは、結局は人々の生きる社会に実装されなければ意味が無いという理念のもと、伝統産業にAIを活用する、アートをAIで作るなどのプロジェクトを行ってきました。
伝統産業にAIを導入する足掛かりとして、地方で活動する様々な伝統産業の「匠」とのつながりを作ることが必要でした。そのために商工会などとの関わりを深めるということを考える際に、酒蔵というコメが価値の基準だった頃からの繋がりを持ったコミュニティへアプローチすることで、酒という業種に限らず人脈を広げていったそうです。
酒を製造する際に必要な様々な工程の中で、最も改善したい、大変だと考えられている吸水という工程にAIを導入し、時間や重量などを細かく計っていた部分をAIによる画像認識で解決することによってその工程を以前より簡単に行えるようにする。その工程、作業をAIで行うことが最善の選択なのか、AIをどのような工程に実装するのが成功なのかを大切にしていると三浦氏はおっしゃっていました。

AIの社会実装について
人工知能とよく言うが知能とはそもそも何なのか、人の知能よりも優れているのか、AIが得意、苦手なことは何なのか、条件や制約はあるのか、実際に人の役に立てるのか等、AIの社会実装については、様々なことを考える必要があります。AIと一口に言っても、「強いAI」と呼ばれる、自分で考え行動するものと、「弱いAI」と呼ばれる、特定の問題解決を自動的に行うことに特化したものが存在します。今この世界に存在するAIのほとんどすべては「弱いAI」ですが、シンギュラリティなどの話題性の強い問題視から、AIに警戒感を持つ人も多いそうです。
最近話題となっているディープラーニングとは、AIの研究分野の一つである認識と言うジャンルのそのまた一部です。そんなディープラーニングが行われるようになって以降、AIの画像認識の性能が大幅に向上しました。が、結局AIは人が決めた成功の条件に則って作業を行う程度のものでしかありません。
これらを踏まえると「人も含めた意思決定の手段がない状態で、困っている人自身に、どうしても解決したいと考えてもらえており、解決の方法がAIしかない」という状態が、最もAIが手段として受け入れられやすいそうです。
AIによるアート
株式会社imaでは、事業の一環としてAI MuralというAIの壁画を作るというプロジェクトを行ったそうです。AIにアートを学習させるにあたって、人類の中で最も古いアートであるクロマニヨン人の壁画から始まり、様々な「価値のあるもの」をインターネット上から探してくるようにAIに指示を出し、探し出した「価値のあるもの」をAIが線画におこします。
その作業をAIが繰り返してアートを作成している最中に人間がしていることといえば、AIが絵を描き終わるのを待ち続け、絵を描くための板を交換するというだけです。これは、やがてはクリエイティブな仕事すらもAIが担うようになり、人間がAIに使役され、単純作業に従事させられるという未来を表現しているのだそうです。
また、AI Muralというプロジェクトの中で「価値の高いもの」を探し出したAIは幾度も人間の著作権や肖像権を侵害しました。AIによる権利の侵害はどのように扱われるのかなどの問題も、AI Muralでは表現されているのです。
さいごに
考え方の根幹にあるものとして、人が好きかどうか、人は面白いなと思えるかどうかを大切にしてほしい。結局のところ、人が働き、人の生活がある。テクノロジーを重要視し、今後の社会にはAIを含めたテクノロジーがどんどん進出してくるからこそ、人にしかできないことを大切にしてほしいと三浦氏はおっしゃっていました。自分も、これから大学で学ぶにあたって「AIにできないようなこと、自分という人間だからできることは何なのか」という新しい視点からコンテンツ製作を考えるようにしたいと思います。