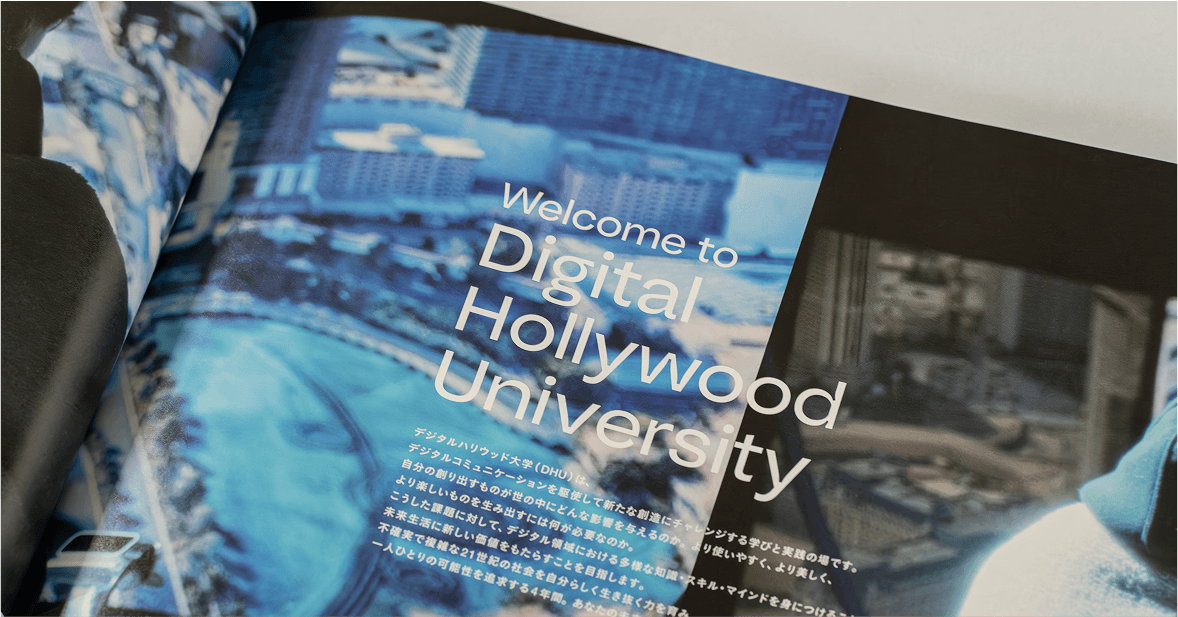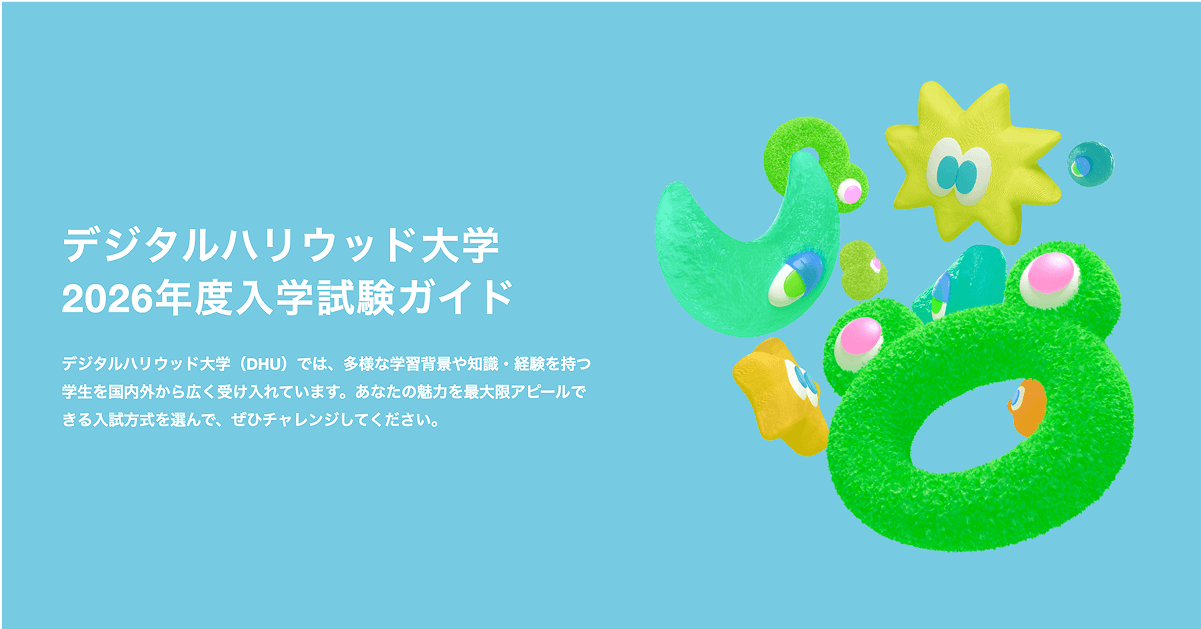ニュース&イベント
【開催レポート】特別講義「日本一の企業から学ぶ!AIやブロックチェーン技術によってクリエイターの価値を高めるには?」

【開催レポート】特別講義「日本一の企業から学ぶ!AIやブロックチェーン技術によってクリエイターの価値を高めるには?」
2025年9月26日、デジタルハリウッド大学は特別講義「日本一の企業から学ぶ!AIやブロックチェーン技術によってクリエイターの価値を高めるには?」を開講しました。
共創施設「SHIBUYA QWS」で活動する本学4年、伊藤 詩奈さんが中心となって特別講義を企画し、同施設で交流があるジャスミー株式会社 取締役 CFO/ジャスミーラボ株式会社 代表取締役の原田 浩志氏をお招きしました。
ジャスミーは2016年に創業した、IoT向けのプラットフォームおよびソリューションを提供する企業です。日本発のプロジェクトとして、発行する暗号資産が2024年12月には時価総額が4,000億円を超え、ブロックチェーン分野で日本一の企業になりました。
本講義で原田氏は、自社の事例をもとにクリエイターとしての価値を高める方法を紹介。また、在学生にとってまだ馴染みが薄い、ブロックチェーン技術に触れるワークショップも実施しました。
ここからは特別講義の様子をダイジェストでお届けします。
1. 情報発信を通じてコミュニティを拡大させる

「今日の特別講義で伝えたいのは、自分の周りにファンを作り共創しましょう、ということです。ファンがプロダクトの幅を広げ、今後の制作・事業活動を変えてくれます。共創というと、お客様の声をプロダクトに反映させるだけだと思っていませんか?」
特別講義の冒頭、原田氏は参加者に向けてこう問いかけました。
では原田氏が考える共創とは何なのか。ファンを獲得し、プロダクトの開発や作品の制作を進めるためにはどうすればいいのか。4つのステップを紹介しました。
1つ目のステップが、情報発信です。ジャスミーはXを中心にコミュニティを形成し、国内外合わせて数十万人のフォロワーを獲得。原田氏は、ファンを獲得するために必要な要素をいくつか紹介しました。
「まず大事なのはアカウントを保有する本人だけが発信者となること。発信する事実は何でもいいのですが、それに自分の意見も載せましょう。情報に個性やストーリーが合わさると、それに対する第三者の意見や解釈が集まりやすくなります。また、コミュニティからコメントが来たら全力で返してください。もれなくすべてに返す必要はありません。コメントをしたら中の人が返してくれるかも、と期待してもらうのが重要です」
コミュニティには、3種類の人が属していると原田氏は言います。それは発信者、投稿を見ているだけ、あるいはたまにコメントをする参加者、そして熱狂的なファンとなるコミュニティリーダーです。
原田氏は熱狂的なジャスミーのファンを“アンバサダー”と呼び、Xのスペースやオフラインのイベントなどで交流を続けたと言います。彼らが強力な発信者となり、自分事として活動してくれることで、ジャスミーのコミュニティは拡大していったそうです。
2. 作品の価値を保存する
ファンとのコミュニティを形成しながら制作を進めるため、次に必要なステップが価値の保存です。
作品を公開してプロジェクト終了、ではなく、その先も作品を管理する必要があります。公開したデータが誰かにコピーされ、あたかも自分の作品かのように無断転載されないために、原田氏は、自分の作品であると証明する方法としてNFTを提案しました。
NFTはブロックチェーン技術を活用した代替不可能なトークンのこと。デジタルコンテンツの所有者が誰なのか、その唯一性を証明するために使用できます。
「ブロックチェーンの世界は中央集権的ではなく分散型です。作品の権利を分散し、みんなのものとして保有することもできます。またブロックチェーン技術を使うと、各所に置かれたサーバーに暗号化した上でデータが保存され、秘密鍵がなければデータの詳細にアクセスできません。ひとつのサーバーにアクセスが集中せず、データを改ざんされるリスクも少ない、価値を保存するには最適な方法です」
画像や動画、デザインなどのデータを保存し、それを価値に変える技術を原田氏は紹介しました。
3. 新技術を活用し、制作プロセスを変える

3つ目のステップが、新技術の活用です。原田氏は、ブロックチェーン技術を活用し、コミュニティの参加者がより自分事としてプロジェクトに参加できる例として、分散型GPUクラウド「JANCTION GPU POOL」を紹介しました。
3DCGのレンダリングや、AIによる画像や映像のアップスケーリング(高画質化)の際に課題となるのが、待機時間の長さです。端末内にあるGPU(画像処理装置)によって描画に必要な計算がされるため、その最中にはほかの作業が制限されてしまいます。
この課題を解決するのが「JANCTION GPU POOL」であると原田氏は言います。
「僕らは、個人が持っているGPUや、データセンターの中で有休状態になっているGPUの演算能力と、分散型GPUを必要としている人をマッチングするためのプロダクトを開発しました。レンダリングのために丸3日かかるとして、ベリファイヤー(実証者)と呼ばれる人の力を借り、700台で同時にレンダリングを走らせればたった6分で完了してしまいます。利用者はその対価を検証者に支払う必要がある一方、作業を大幅に短縮できたりバックグラウンドで作業できたりするなどのメリットを享受できます」

また原田氏は、ブロックチェーンに限らず、コミュニティ参加者が新しい技術に触れることが重要であると言います。発信者が日々新しい技術を追い求め、その技術をコミュニティに共有する。「新しい刺激を得られている」と感じてもらうことが、コミュニティ参加者の満足度に影響すると解説しました。
4. 独自の経済圏を構築する
4つ目のステップが、経済圏の構築です。コミュニティ参加者がただの消費者に留まらず、作り手のひとりになったり、作品の権利を所有する人になったりすることが大切であると原田氏は言います。
実際に、大勢のクリエイターがひとつの作品を作った例として、ある動画を紹介しました。それが、『2,400 artists create unique renders from a simple prompt』という作品です。
制作者は2,400人のクリエイター。制作期間は18年。画面左から右へ、何かを引っ張る人の3DCG映像を、1人あたり数秒制作し、それをモンタージュしたそうです。
「一つひとつの作品をバラバラに公開したら、見る人は少ないかもしれません。ですが、全員の作品をつなげると広告収入を生むほど視聴される作品になります。このような作り方をすると、作品の再生回数が増え広告収入が生まれるだけでなく、“この人に仕事を依頼したい”と新たなチャンスを創出する場合もあります」
原田氏は、作品の権利を所有しながら、出会いや仕事を得られる、新たな経済圏の一例を紹介しました。
ブロックチェーンに触ってみよう
特別講義終盤には、NFTの制作を通じて、ブロックチェーン技術に触れるワークショップが行われました。
使用したプラットフォームは、暗号通貨「Ethereum(イーサリアム)」ベースのブロックチェーン「JASMY Chain」。このブロックチェーン(分散型台帳)に、コンテンツの情報や、所有者の情報などが記録されます。
ブロックチェーンから発行される証明書がNFTです。NFTを保管するためには、銀行口座のようなウォレットが必要になります。
今回のワークショップでは、MetaMaskというウォレットのアカウント開設からスタート。これで、NFTや暗号資産(仮想通貨)を保管できるようになりました。
それから、デジタルコンテンツをブロックチェーンにアップロードをする際に便利な「Pinata」を使用し、NFTとなる画像をアップロード。ノーコードで作業できるとはいえ、やや苦戦する参加者の皆さん。原田氏やジャスミーのスタッフの力を借りながら、ブロックチェーン技術を体験しました。
新しい技術に触れると世界がひらける

最後に、原田氏から参加者にメッセージが送られ、特別講義が終了しました。
「今日は主にブロックチェーン技術を活用したコミュニティのあり方について紹介し、ブロックチェーン自体に触れていただきました。馴染みがない方にとって、未知のプラットフォームを使い、自分の作品を不特定多数の人に見られるのは怖いと思うかもしれません。ですがこれを機に、自分が持っている権利を積極的に証明、保護し、価値に変えていくんだというマインドセットになって、新しいことにチャレンジしていただきたいです。今回は画像をNFTにしただけでしたが、動画やキャラクターなどいろいろなものをNFTにできます。まだまだ可能性のある分野だと思うので、一歩踏み出して、自分なりに行動していただければ嬉しく思います」
*
今回の特別講義を主催した伊藤さんが所属している be♭(ビーフラット) は、「コミュニケーションのおもちゃ屋さん」をコンセプトに活動する学生団体です。
初対面でなかなか話が弾まない、会議で意見が出てこない。
そんなコミュニケーションのお困りごとを、楽しく軽やかに解決するおもちゃ「TOY」を開発しています。Instagramや展示会など、発信活動にも力を入れていますので、ぜひチェックしてみてください!
be♭公式Instagram:https://www.instagram.com/be.flat_toy
デジタルハリウッド大学では今回のような特別講義を通じ、学生自身のキャリアを考える機会を設けています。
オープンキャンパスでは本学の実務家教員による体験授業や、学外のクリエイターによる特別講義などを開催しています。ぜひイベントにご参加ください。
https://www.dhw.ac.jp/opencampus/
デジタルハリウッドで講義をしてみたいという企業様、クリエイター様、研究者の方は、本学事務局へお問い合わせください。
デジタルハリウッド大学事務局(特別講義担当)
dhu@dhw.ac.jp